自由に生きる。
とても素敵な響きを持つ言葉ですし、そこを追求することも大切なことだと思います。でも、自由と思って振る舞っていたつもりが、それは好き勝手で野放図なだけで、気が付けば自分の周りから人が離れているなんてこともあり得るかもしれません…。
では、自由とは何なのか。
これこそが正解だ!みたいなことを言うつもりは一切ありません。ありませんが、なんとなくこんな感じじゃないですか?というたたき台のようなものを提示できればと思い、書いてみました。
自由に生きることの大切さ
自由とは何かを語り出すと長くなりますし、そんな壮大な話を僕ができるわけがありません。
そのあたりの概念的なことはミルの「自由論」などの著名な書籍を読んでくださいと茶を濁す感じが一番良いと思うのですが、それだと乱暴すぎる気もしますので、自由が僕たちに大切である理由となるものをいくつか紹介したいと思います。
総じて言えば”自由だから幸福を感じられる”ということに尽きると思っています。つまり、自由とは幸福の源泉です。
そう言える理由をいくつか紹介します。
自己決定理論
1つは自己決定理論と呼ばれるものです。
自己決定理論の根幹を支える3つの基本欲求は「有能感」「関係性」「自律性」である。
有能感の欲求とは、「自分には能力があると感じたい」という欲求である。これは、自分には能力があり、社会の役に立っていると感じられたいためである。
関係性の欲求とは、「他者と精神的な関係を築きたい」という欲求である。これは、他者と尊重し合う精神的な関係を築きたいためである。
自律性の欲求とは、「自分の行動は自分で決めていると感じたい」という欲求である。自分の行動は自分自身が自発的に行なっているものであり、他者から強制されているのではないと感じられたいためである。
3つの欲求の中でも自律性が最も重要視されており、「行動を自ら決定した」とより強く感じられると心理的な満足感が高まる。
自律性、能力、関係性という基本的な欲求を満たすことで幸福感などが高まるとする理論です。この中の自律性というのは自由であるということを定義していると捉えても良いかと思います。
自分で決めるということが幸福と直結するので、自分で決められる自由はすべての人が幸福に生きるためにとても大切なことでもあります。
自由は生きる理由や希望になる
アウシュビッツでのホロコースト体験を語った書籍「夜と霧」の中でも、刺激と反応の間にある選択の自由こそが”自由”であるともされています。
誰かに自分がどうするのかを決めさせるのではなく、自分で自分の在り方を決めることこそが自由だ!みたいな。
当時のナチスにアウシュビッツ収容所に強制連行され、ユダヤ人を撲滅するという人類史上でも類を見ない異常な目的のために行われた大量殺人行為ホロコースト。その環境下の中、絶望の中で、著者は「生きて帰り、家族とともに幸せに過ごす」ことのみを想像し、正気を保って生き延びることができたとされています。
どのような環境や境遇の中でも、その環境に屈するのか、それとも自分の中で違う反応を選ぶのかは自分次第である。絶望を選ぶのか、希望を選ぶのかは自分次第。そういう意味で、刺激と反応の間にこそ”自由”があるとしています。
自由は幸福につながるが不幸にも繋がる
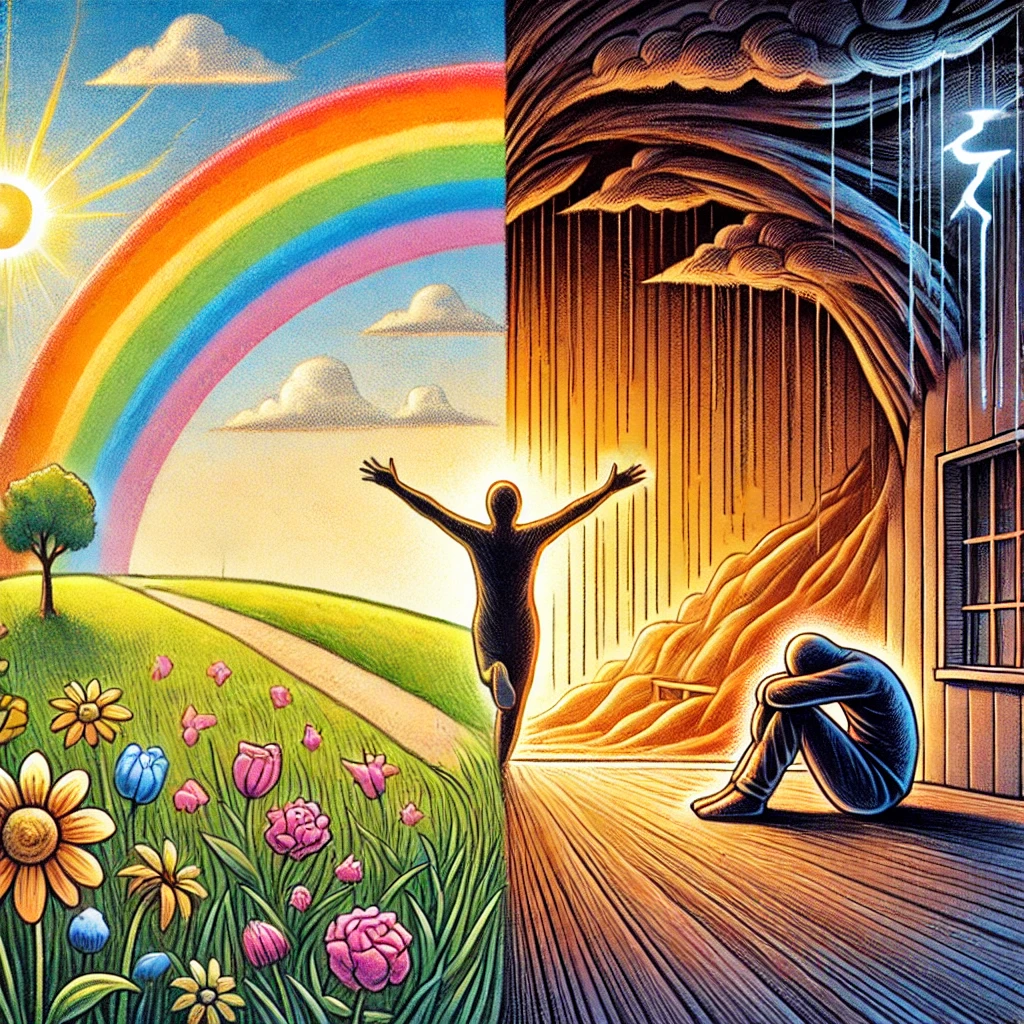
自由とは何かを簡単に言えば”選択できる”ということを指す。そしてなぜそれが大切なのかというと、個々人の幸福に直結しているためです。
「ごはん何を食べようかな?」と思い、何を選ぶのかは自由であり、幸せでもあるということです。実際、自分でごはんを選んで食べられるのは幸せですよね?
しかし、僕自身が自由に生きすぎて不幸を実感したことがあるという体験がそれだけで結論付けるのを良しとしません。
そこで自由についてもう少し深堀すると、次のようなことが考えられるんじゃないかな?とも思うんです。
自由の概念の誤解
1つは、自由の概念の限界です。
例えば、他者の権利を侵害するのも自由の範疇だとなると、これは相手との間に摩擦を生みます。下手をすると争いにまで発展します。
例えば、すべての土地は「ここまではAさんの土地、ここからはBさんの土地」と決まっています。
基本的に、その境界線を越えなければ問題は起きません。Aさんが自分の土地で何をしてもBさんは怒りません。しかし、Aさんが境界線を越えてBさんの土地で何かを行えば問題が生じます。
境界線の中で何をしてもいいけど、境界線を越えても何をしても良いという事ではありません。
また、自由を優先するあまり義務を怠ると問題につながります。働かないであったり、納税しないであったりも自由の範疇だと考えてしまうと、最終的にはとんでもないツケを払うことになります。
つまり、自由の限界を誤解してしまうと問題が起きます。
こういう事を踏まえると、自由とは「他者の同意のもとに存在する」と言い換えることもできます。
僕たちは社会という集団の中で活動するのですから、自分と自分以外の人たちの関係性が必ずそこに発生します。その中で自由なふるまいを取ろうとすることの大前提は、集団が許す範囲の自由ということになると思うのです。
自由は大切であるが、同時に、自由を行使するためには守らなければいけないルールがあるとも言えます。
2種類の自由
そこで思うのが2種類の自由です。
- 内側の自由:自分の心の中での選択の自由
- 外側の自由:社会が許す範囲での選択の自由
ごはん何を食べようかな?と悩み、今日はこれを食べようと選ぶ自由が内側の自由です。しかし、その食べたいものが1,000円で売られているとして、手持ちに500円しかないとします。そこで500円だけ払ってその1,000円の料理を食べることは許されません。
自由には内側の自由と、外側の自由の2種類があります。
イザヤ・バーリン (Isaiah Berlin)って方が自由論としてすでに2種類の自由を定義していて、そちらのほうが分かりやすくてスマートな考え方なのでそちらを参考にすると自由は次の2種類があるとなります。
- 消極的自由:他者からの干渉がない状態
- 積極的自由:自己実現の自由
僕が先ほど書いた2種類の自由とこの2種類の自由をかさねて透かして見てみると、なんとなく僕が言いたい事がわかるかとも思います。
自由には内側での自由と、外側に向けて発露する自由の2種類の自由があります。
その2種類の自由があることを認識していないと、”自由に生きる”の意味は全然違ったものになってきますし、その認識違いが自由によるデメリットやリスクに繋がっています。
自由についての論文や名著
また、自由についてまとめられている理論や論文や書籍は多数あります。
中でも著名なものに絞り込んで、その中でどういう事が語られているんかをまとめると得られる知見もあるのでは?ということでまとめてみました。
| タイトル | 著者 | 発表年 | 概要 | 参考文献・リンク |
|---|---|---|---|---|
| 「自由の二つの概念」 (Two Concepts of Liberty) | イザヤ・バーリン (Isaiah Berlin) | 1958年 | 自由を「消極的自由」(他者からの干渉がない状態)と「積極的自由」(自己実現の自由)の二つに分類し、それぞれの概念が社会や個人に与える影響を論じています。 | ウィキペディア |
| 「市場と自由」 (Markets and Freedom) | ミルトン・フリードマン (Milton Friedman) | 1962年 | 経済的自由が市場の効率性や個人の自由に与える影響を論じ、自由市場経済の利点と政府介入の限界を分析しています。 | Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom. University of Chicago Press. |
| 「正義論」 (A Theory of Justice) | ジョン・ロールズ (John Rawls) | 1971年 | 社会における正義の原則を定義し、自由と平等のバランスを探求。特に「最大最小原理」を通じて、社会的・経済的不平等が最も恵まれない人々に利益をもたらす場合にのみ許容されるべきと論じています。 | Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press. |
| 「自由と権威」 (Freedom and Authority) | バートランド・ラッセル (Bertrand Russell) | 1953年 | 自由と社会的権威の関係を哲学的に探求し、個人の自由が社会の発展と調和するための条件について論じています。 | Russell, B. (1953). The Impact of Science on Society. London: George Allen & Unwin. |
| 「自由の概念」 (The Concept of Freedom) | アルフレッド・ノース・ホワイトヘッド (Alfred North Whitehead) | 1939年 | 自由の哲学的概念を探求し、個人の選択と社会的構造との関係を分析。自由がどのようにして人間の行動や社会の発展に寄与するかを論じています。 | Whitehead, A. N. (1939). The Concept of Freedom. Mind, 48(190), 470-485. |
| 「自由と道徳」 (Freedom and Morality) | ジョン・スチュアート・ミル (John Stuart Mill) | 1859年 | 個人の自由と社会の道徳的規範とのバランスを論じ、他者に害を及ぼさない限り、個人の自由は最大限に尊重されるべきであると主張しています。 | Mill, J. S. (1859). On Liberty. John W. Parker and Son. |
| 「自由の経済学」 (The Economics of Freedom) | フリードリヒ・ハイエク (Friedrich Hayek) | 1944年 | 経済的自由が市場の効率性やイノベーションに与える影響を論じ、計画経済のリスクと自由市場経済の利点を対比。自由主義経済の理論的基盤を築きました。 | Hayek, F. A. (1944). The Road to Serfdom. Routledge. |
| 「政治的自由と社会的制約」 (Political Freedom and Social Constraints) | アマルティア・セン (Amartya Sen) | 1999年 | 政治的自由と経済的発展の関連性を分析し、自由がどのようにして社会全体の繁栄に寄与するかを論じています。 | Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press. |
| 「自由と責任」 (Freedom and Responsibility) | ダニエル・デネット (Daniel Dennett) | 1984年 | 自由意志と責任の関係を探求し、個人の行動における自由の役割とそれに伴う倫理的責任について論じています。 | Dennett, D. (1984). Freedom Evolves. New York: Viking Press. |
1つ1つを解説するのはとてもハードルが高い行為なのでそんなことをするつもりはありません。ただ、いずれの論文や理論も伝えたいことは次のような点にまとめることができるかと僕は思っています。
- 自由には責任が伴う
- 自由は社会との調和を大切にすべき
色々な角度で自由について述べられていますが、いずれも自由だけを追求すると社会がダメになるよ、でも、自由が社会を発展させるのも事実だよ、だからバランスが大切だよってことが書かれています。
そのバランスを見極める上で、自由がアクセル、責任がブレーキみたいな視点での捉え方が為されているのかな?なんてことも思います。
責任を取ろうとしない自由は、公道で何キロで車を走らせてもいいでしょ?ってことになります。当然、それによって事故を起こすリスクは高まりますし、事故に巻き込まれる可能性も高まります。
だから、スピード制限を設けて、その範囲内で走らせるようにという交通ルールを作ります。
思いっきりスピードを出したい、出せばどうなるのかな?と思うのは自由です。しかし、それを外側に向かって発露するときは、その集団のルールがそれを許すのかどうかが付きまといます。
自由に生きてきたつもりが状況が悪くなっていると感じるなら、それは負うべき責任を負ってこなかったからでは?集団が許していない行動を繰り返したからでは?ということも考えられます。
自由と責任をもう少しだけ理解するために

自由とは何かとなると、内側の自由(何を思うのか、どう感じるのか)と外側の自由(どういう行動をするのか)の2種類があります。そして、そのいずれにも相応の責任がつきまとうことになります。
その2種類の自由に対して自分がどう責任を取るのかまでを併せて考えて、初めて自由に生きることができる資格を得る。これが模範解答であり最適解だと思います。
ただ、個人的には自由に関する責任に関しては、少し手前の部分の”心構え”を整えることが大切なんじゃないかな?と思うんです。例えば次のような感じです。
- 内側の自由 : どう思うのかも、どう感じるかも自分次第
- 外側の自由 : 行動できる範囲は属する集団のルールに左右される
何をどう思っても、どう考えても良いけど、それは全て自分次第だと自覚する。良いように考えるのも、悪いように考えるのも自分次第。不快に考えるのも、楽しくなるように考えるのも自分次第。
どういう行動を取れるのかは属する集団によって左右される。例えば、日本で許されることが海外でも許されるわけじゃないし、その逆もまたしかり。許されることの範囲は属する集団で左右されるので、それを可能な限り把握する。
そこを理解し、踏まえた後にこそ自由であることができるんじゃないかな?と思うんです。
つまり・・・
自由に生きるというのは、内側の自由は自分次第で、外側の自由は互いの許可の範囲内(要するにルール)であるという認識を持って生きるという事だと思っています。
逆に言えば、無責任な自由、いわゆる野放図や好き勝手というのはこういう事なんじゃないかな?とも思います。
- 自分の思考や感情を自分でコントロールできず、暴走する
- 社会的に許されてない行為だけどやりたいからやる
端的に言えば、こういう事を指していると思います。
なので、まずは内側の事は自分次第、外側のことは共通認識次第だと自覚する。そして、その前提で自分の幸福感が高い選択肢を選ぶことが自由な生き方ということになるんじゃないかな?なんて思います。
例えば、これを読んで「なるほどね」とあなたが思うことも「違うよね」と思うことも自由です。良い点を見つけるのも、悪い点を見つけるのもあなたの自由です。
ただ、「お前の言う事は違うぞボケ!」と僕に届くように言った途端にそれは表現の自由を超えて誹謗中傷になります。
当たり前だよねって思う人が大半だと思うけど、自由の領域設定がバグっていると、自由に生きたつもりが自分自身の首を絞めることになっていきます。
だから、内側の自由は自分次第、外側の自由はルール次第ということを踏まえ、その前提の下で自分自身が幸福を感じる選択をしていくことが自由で幸せな生き方なんだと思います。
1つの考え方として、あなたの一助としてお役立ていただければ嬉しく思います。

コメント